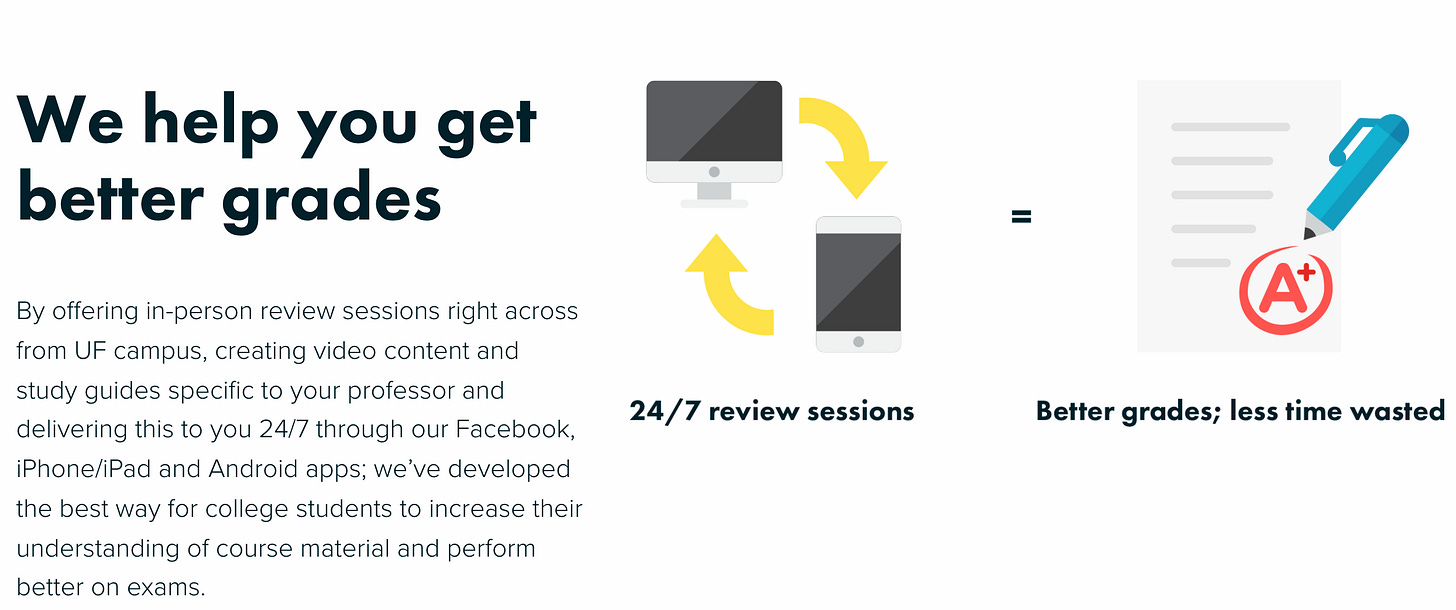2022年もImpactShareをよろしくお願いします!登録者が500名を超え、執筆者一同、身の引き締まる思いです。
今年の1本目は、EdTechについてです!インパクト投資界隈でもよく耳にするEdTechは、テクノロジーの力を駆使して様々な教育サービスを提供しています。最近では、コロナ禍で学校が閉鎖され教育が止まるという危機に対応したことで注目を浴びています。本記事では、EdTechの事例を取り上げながら、インパクト投資におけるEdTechの論点について考えていきたいと思います。
EdTech代表的な事例
例えば、米国のEdTech企業のStudy Edgeはオンラインの家庭教師・教育サポートを提供し、MainstayはAIを駆使してチャットボットで学校側の問い合わせ対応を自動化させました。
また、Packbackは対面式で自然発生するディスカッションなどをオンラインの場でも増やすために、生徒たちの会話をファシリテートするサービスを提供しています。(余談ですが、Packbackのサービスは、「良い問いを立てる」スキルを身につけられるように設計されているようで、MBA留学などに役立ちそうです…)
このように、コロナ禍で急速・急激に変化した教育の場の様々な場面でEdTech企業は生徒、先生、そして親へのサポートを提供し、生徒が学びを続けられる環境を提供しています。オンラインでの教育の質の向上にも貢献しています。
インパクト投資とEdTech
EdTechへの需要は、特にコロナ禍で増していますが、インパクト投資業界での運用額シェアでは、EdTechは他のインパクトセクターと比べて非常に小さいのが現状です。GIINが発表した2020年アンケート調査によると、全体の3%で決して大きくありません。その背景の一つとして、インパクト投資の投資対象として、EdTech企業の固有の事情があると推察されます。

EdTech企業になぜインパクト投資しにくいのか?
教育業界は、政府など、重要なステークホルダーが多数存在するため、学校へサービス・プロダクトを提供するEdTechは特に様々なステークホルダーから理解や協力を得ることが重要となります。ビジネスの立ち上げ、うまく回していくためには、多くのコミュニケーションコストがかかったり、事業展開上の制約が加わったりすることもあると言われています。
実際に、2021年、中国で成長していたEdTech業界にブレーキがかかりました。
当時、世界EdTechユニコーン32社のうち、8社は中国企業でした。ところが、2021年に大きく一変し、中国政府がテック大手に対して規制を強化をしました。その波はEdTechにも及びました。具体的には、2021年7月、小中学生向け学習塾の非営利組織への転換するよう方針を打ち出したり、該当企業に対してIPO禁止、海外投資家からの投資受け入れ禁止や、6歳以下に対するオンライン塾・家庭教師サービス禁止などが公表されました。
こういった中国での動きの背景には、公的な要素のある教育を民間が担うことによって金儲けの手段になっているのではないか、その結果として必要以上のサービスを受けるコストが上昇しているのではないか、格差社会が深まる中国で質の高い教育へのアクセスを阻害しているのではないか、こういった問題意識があるようです。
このような問題意識は中国に限った話ではありません。以前ImpactShareでもご紹介した、Bridges International Academiesでも貧困層向けの学校を民間が提供することに対しての批判が一部ありました。
教育企業に投資をする国際NGO、Luminos Fund CEOのBaron氏は「投資家としてスケールを重要視すべき一方で、教育業界では急速な成長はリスクでもある。 営利企業が教育業界で利益を得ることが問題視されることもある。」と指摘しています。
EdTech企業の工夫
こういった考え方があるとはいえ、世界のEdTech企業は、生徒や親だけでなく、地域社会などのステークホルダーのニーズを満たすようにビジネスモデルを工夫したり、ビジネスをスケールさせることによってサービス価格を下げようという、挑戦がされています。
EdTechのビジネスモデルは、サブスクリプションモデル、マーケットプレースモデル、スポンサーシップモデルなど多岐にわたります。
また、あえて学校外での教育サービスを直接生徒に提供するEdTech企業も多数存在します。
以下では、フリーミアムモデルと、受益者である生徒ではない他社から売上を創出するビジネスモデルを構築している事例を紹介します。
アメリカ企業の事例 Schola
Scholaは、ユーザーに対して学校検索ツールを無料で提供している、アメリカ企業です。「生徒を理想的な教育環境に置くことで、教育成果を向上させること」をビジョンに掲げています。同社は、インパクトとリターンの追求を掲げるPortfoliaなどから出資を受けています。

どこでお金を稼いでいるかというと、生徒数がなかなか集まらない学校(特に、公立学校)から一定の料金をもらっています。学校の特徴にあった生徒を確実に確保できるように各種マーケティングツールや入学まで生徒を徹底的にサポートするというサービスを学校の代わりに提供しています。

ここで、こういった学校からフィーを得ることを懸念する声もあるかもしれません。しかし、アメリカの公立学校は政府からの公共収入源の一部が生徒数と比例するため、Scholaの使用により生徒数が一定数以上確保できれば、Scholaに支払う対価以上の収入を学校が得られるモデルとなっている点が特徴です。
生徒数が減ると教育現場の予算が削減されてしまい、教育環境の質にも影響します。生徒数を確保できないと、既存生徒に提供している教育の質も低下してしまうかもしれません。同社は、Schola使用で実際に入学した生徒達へのインパクトを定義して測定することが今後の課題となることが考えられます。
日本における今後の可能性
コロナの影響もあり、世界で教育のあり方とテクノロジーの活用が加速する中、日本でも今まさに教育が変化の時を迎えていると言えるかもしれません。文科省による「GIGAスクール構想」により、小・中学生一人一台のパソコンやタブレット端末の配布やWifi環境整備などが2020年から始まり、経産省は学校のEdTech導入を促進する「EdTech導入補助金」を打ち出しています。
アメリカの教育分野のインパクト投資家、New Market Venturesは「最高の教育会社というのは、サービスを提供する学生のニーズと投資家の目標である金銭的リターンの創出を一致させることに成功している会社だ。」とコメントしています。インパクト投資家は、EdTech企業と共に、インパクトを持続的に実現できるビジネスモデル構築やインパクト・マネジメントとガバナンスを強化することにより、教育の質・アクセス向上に貢献することが期待されています。
【参考資料】
Global EdTech Funding 2021 - Half Year Update (6/28/2021, HolonIQ)
How China’s tightening rules for private tutoring affect foreign teachers (8/8/2021, Global Times)
New Market Ventures 2020 Impact Report (New Market Ventures)
Why Impact Investors Shy Away From Education (2/8/2019, BRIGHT)
Photo by National Cancer Institute on Unsplash